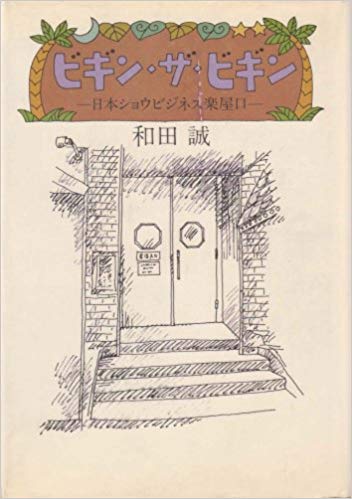
『ビギン・ザ・ビギン-日本ショウビジネス楽屋口-』 和田誠 著 文春文庫・刊
この十月に、イラストレーターの和田誠さんが亡くなった。シンプルで味わい深い和田さんのイラストは、週刊文春の表紙を長らく飾っていたので、ご存知の方も多いと思う。週刊文春の編集長は、追悼のコメントとして「これまで和田さんが描いてきたイラストがたくさんあるので、今後も使っていく」と述べていた。
和田さんは文字通り多才で、イラストの他にも煙草のハイライトのパッケージ・デザインをしたり、映画にも造詣が深く、小泉今日子主演の映画『快盗ルビイ』を監督してブルーリボン賞を受賞している。
そして全盛時代の日劇のレビューを演出した山本紫朗は和田さんの伯父にあたり、山本氏に取材して書いたノンフィクションが『ビギン・ザ・ビギン』である。若き日のダニー・ケイや、初期の日劇ダンシングチームのスター、根岸明美、舞台監督だった森繁久弥などがキラ星のごとく登場する。和田さんはこの本で、角川書店日本ノンフィクション賞を受賞したのだった。
本書は、日劇が取り壊されるところから始まる。同時期に取り壊された朝日新聞社の社屋は引っ越しを済ませていたが、日劇は移転をせず、消滅してしまうのだった。和田(以下、敬称略)は大学生時代から日劇にレビューを見に行っていたから、ファンからの視点も含めてスターたちを次々に取材していく。それらを大きな視点で締めるのが、本書での山本の役割だ。レビューの踊り子から映画スターが生まれたり、音楽担当の服部良一が作曲した「東京ブギ」などの曲を笠置シヅ子が歌って大ヒットしたり、日劇の物語とはいえ、さながら戦後の芸能史の様相を呈する。
和田が山本の甥っ子だったからか、スターたちはざっくばらんに裏話を開陳する。たとえば根岸は踊りを辞めた理由を、踊っていてある振り付けになると必ず膝の関節が外れてしまうようになったからだと告白する。「今度の日劇の最後の舞台も、出てみたいなあ、と思いましたよ。でも、脚がはずれちゃったらなあ、と思うし」。赤裸々な言葉が、胸に刺さる。
かと思うと、「横浜に六つくらいの子でうまいのがいるよって言うんで、横浜へ行ってきたんです。(日劇に出したら)笠置さんも灰田(勝彦)さんも、みんな食われちゃって。お前、変なもん連れてくるなよ、って言われちゃった」と山本は語る。この歌の上手い子が、美空ひばりだった。
とにかくエピソードが面白い。その間に挟まれる和田の感想がまた面白い。レビューの表舞台だけを見て楽しむのもいいが、それだけでは見えない裏方の才能と工夫を探り当てる和田の筆運びが見事だ。
そして本書のタイトルになった「ビギン・ザ・ビギン」は、コール・ポーターの作った名曲で、この歌にまつわる章の主役として越路吹雪が登場する。終戦から3年が経ったころ、山本はあるパーティで越路を紹介された。越路は初対面の山本に「踊りませんか」と声を掛け、そのとき流れていたレコードの「ビギン・ザ・ビギン」に合わせて二人は踊ったのだった。
しばらくしてコール・ポーターの伝記映画『夜も昼も』が日本で封切られることになり、その試写会に山本は越路を誘う。「もちろん行くわ」と答えた越路は、映画を観終わってから、ひと言も発しなかった。「どうしたんだ?」と山本が尋ねると、越路は「いましゃべると、感激がこわれちゃうのよ」と言い放つ。
この台詞の生々しさは、どうだ。和田の聞き書きの技術の高さがあってこそのものだが、越路の気風のいい返答が快い。越路は余韻を楽しみたかったのだった。
「目つむれば蔵王権現後の月 阿波野青畝」(季語:のちのつき 秋)
俳句は余韻が大事と言われるが、青畝はこの句で余韻そのものを詠んでいる。その日に見た蔵王権現を目を閉じて心の中で再生すると、感慨は深まる。越路はその後、何度も「ビギン・ザ・ビギン」を歌って絶賛されることになるのだが、その歌唱に先の映画の余韻が影響したことは想像に難くない。その他、本書には「日本ショウビジネス楽屋口」と副題が付いているように、楽屋からしか見えない景色がたくさん収録されている。
「橋なくて日ぐれんとする春の水 蕪村」(季語:春の水 春)
橋を日劇に置き換えてみてもいいだろう。蕪村は物事の“不在”を詠って名句をたくさん遺しているが、和田は「日劇の不在」を丁寧に描く。気取った芸術ではなく、あくまで大衆を楽しませる芸能は、劇場の不入りという現実を前にして取り壊されていった。
レビューの華やかさと儚さの間に、和田は何を見たのか。豊富なエピソードが語るのは、泥臭くも無垢な日本のショウビジネスの原風景だ。それはある意味、和田が見たかった、虚と実の織りなす美しい人間の波紋だったのではないかと思う。
「踊りたがる、外れた関節」はそのまま詩になっている。この素晴らしい芸能論を書いた和田さんの冥福を、心から祈りたい。
「頬杖の何を見てゐる冬銀河 楸邨」(季語:冬銀河 冬)
俳句結社誌『鴻』2019年12月号コラム“ON THE STREET”より加筆・転載





















