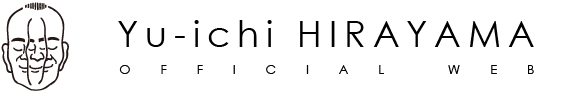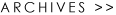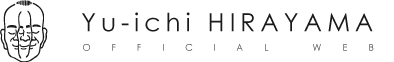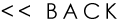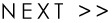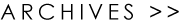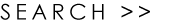『プロデュースの基本』 木崎賢治・著 インターナショナル新書・刊
著者の木崎賢治さんは、僕にとって音楽業界の大先輩である。プロデューサーとして沢田研二、山下久美子、大澤誉志幸、吉川晃司、槇原敬之、ロックバンドではトライセラトップスやバンプ・オブ・チキンなどの制作を手掛け、これまで四十年以上にわたって数多くのヒットを飛ばしてきた。担当アーティストのライブでお会いすると、音楽制作に関する面白いエピソードを聞かせてくれる素敵な方で、そんな時いつも、業界の最前線で生まれた数々の逸話を僕だけが聞いているのはもったいないと思っていた。なので、今回、それが一冊になったことは嬉しい限り。早速、紹介したいと思う。
木崎さんの仕事は楽曲作りから始まる。ある歌手の新曲を依頼されると、イメージに合った作曲家や作詞家、編曲家を選び、レコーディングをする。ここまでは“ディレクター”としての仕事。木崎さんは作ったレコード(今ではCDや配信になっているが)を売るところまで責任を持つ。ここまで来て、初めて“プロデューサー”を名乗ることができる。作曲や編曲は音楽を勉強すればある程度は理解できるが、それが売れるかどうかは人々の心や世の中の様子に敏感でないと判断できない。「楽曲を作る」のではなく、「ヒットを作る」のが木崎さんの仕事だ。
木崎さんのやり方は、他の音楽プロデューサーとは大きく異なる。「二匹目のどじょう」という言葉は音楽業界のためにあるようなもので、何かヒットが生まれると必ず似たような曲が次々に出てくる。しかし木崎さんは必ず新しい挑戦を心掛ける。たとえば八〇年代末のバンドブームのとき、「バンドばっかりだからこそ、ピアノを弾きながら歌うソロシンガーがいいな」と考えて、槇原さんをデビューさせた。
七〇年代末、沢田研二さんがある不祥事から復帰して間もなく、阿久悠さんに新曲の歌詞を頼んだときのこと。上がってきたのは「勝手にしやがれ」という曲だった。ある意味、大胆で不謹慎な提案に、さすがの木崎さんも怖気づいてしまったが、結果は大ヒット。セクシーでカッコいい沢田さんに足りなかった“情けなさ”を足すことで、逆に男らしいイメージが生まれた。「阿久さんはお見通しなんです。忘れ得ない経験です」と振り返る。「勝手にしやがれ」は、阿久さんのプロデュース感覚の方が当たっていたのだった。
木崎さんが特に優れているのは、歌詞作りだ。歌手の持つイメージと時代状況を掛け合わせたところから、歌詞の方向性を決めていく。自分で作詞作曲するシンガーソングライターをプロデュースするときは、その人の言葉の感性を大切にしながらアドバイスを行なう。
「いいものにはだいたい定形があります。そのなかでいかに個性を表現していい作品をつくれるか、それが大事です~俳句だって、五七五の制約のなかで新しいものをつくってきましたし、これからもつくられていきますよね」。突飛な言葉やメロディではなく、普通の言葉を使って人と違うものを作れるのが才能だとも言う。これらの言葉は、まるで『鴻』誌の裏表紙に載っている漫画「栗庵閑話」とソックリではないか。俳句で言えば、平明で個性的な句作りというわけだ。
それにしても、木崎さんが俳句に言及するとは思わなかった。今度、会ったら俳句にどのような興味を抱いているのか聞いてみようと思う。そしてこの本を読んでいて、いちばんハッとしたのは次の言葉だった。
「歌詞とは、心という見えないものを可視化したもの~俳句とも似ています」。
芭蕉の「古池や」の句にしても、ただ風景描写をしているだけでなく、そこに静けさや寂しさや人生のはかなさを表わしていると語る。「心を動かされたときに目に入ってくるものを描くことが基本じゃないかと思います」。どうやら木崎さんの歌詞作りの極意と、俳句にはたくさんの共通点がありそうだ。
「口笛や沈む木に蝌蚪のりてゐし 田中裕明」(季語:蝌蚪 かと おたまじゃくしのこと)
口笛を吹きたくなるほど陽気な時に、作者の目に入ったのは群れ遊ぶオタマジャクシだった。春の胎動は小動物にも人間にも等しく訪れる。
「みえてゐて滝のきこえず秋の暮 久保田万太郎」(季語:秋の暮 秋)
壮大な滝の前に立っているのに、鳴っているはずの水音が聴こえない。滝音は作者の心の中に吸い込まれ、轟々と響いているのだった。秋の暮の凄絶な孤独を、無声映画のような滝の景色が見事に浮き彫りにする。これらの句は、正岡子規の唱えた「写生」から来ていると思われる。「嬉しい」とか「寂しい」とか言わずに、感情を目に入った具体的なモノに託している。
商業ベースで言葉をクリエイトする苦労は推して知るべしだが、本書を読む限り、木崎さんはそれを楽しんでいる。「楽しんで作る」ことが、人の心を動かすのは俳句もポップスも同じだ。だとすれば、自分の句をプロデュースする意識を持って、句作に挑んでみるのも面白い。そんなことを思いながら、槇原さんの名曲「もう恋なんてしない」を聴いてみたらいかがだろうか。“ヤカン”や“紅茶”などのモノが、楽しく語りかけてくるはずだ。
「春風にこぼれて赤し歯磨粉 子規」(季語:春風 春)
俳句結社誌『鴻』連載コラム「ON THE STREET」
2021年2月号より加筆・転載