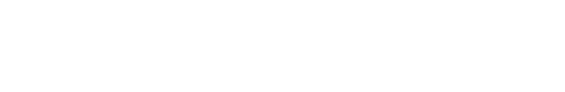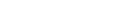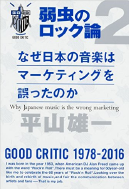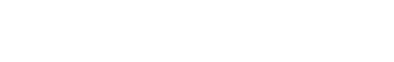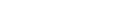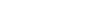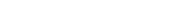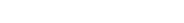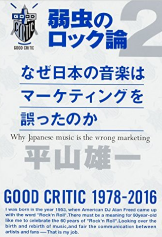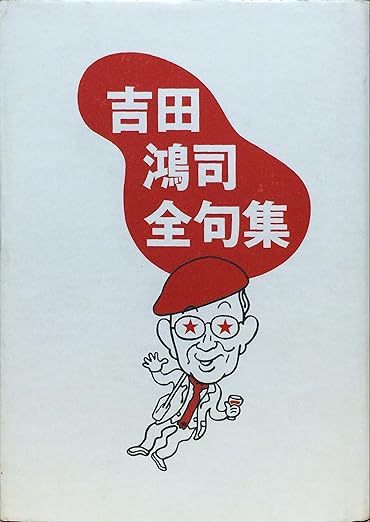
『吉田鴻司 全句集』 鴻 出版局・刊
結社「鴻」の名の由来となった吉田鴻司師が亡くなって、今年で二十年になる。懐かしく感じる方がいる一方で、お会いしたことのない方にとってはあまりピンと来ないかもしれない。が、鴻司師が「鴻」の源流のひとつであることは確かなことなので、この機に師の俳句観と句業を振り返ってみたい。
「油掌洗ふ砂の西日を擦りこみて」(季語:西日 夏)
「脱ぐ手套なほ鉄握る形して」(季語:手套 しゅとう 手袋のこと 冬)
「姥捨や夏天の遠さ母の遠さ」(季語:夏天 夏)
第一句集『神楽舞』からの句。鴻司師は父親の手ほどきを受け、十代から作句を始めた。いくつかの結社を遍歴した後、一時、俳句から遠ざかる。しかし角川書店創業者の角川源義の講演に感激して、四十歳で結社「河」の創刊に参加。本格的な俳人としてのキャリアをスタートすることになる。
師は新興俳句の影響も受けていた。「油掌洗ふ」や「脱ぐ手套」の句には、鉄工所で働いた経験がリアルに描かれている。それと並行して「姥捨や」のように古典に根ざした句も作った。こちらは源義の影響だろう。その上で「河」のテーマである「抒情性の回復」に努めたのである。
「花桃やこんこんと月上りをり」(季語:花桃 春)
「いつぱいに打つては志賀の一枚田」(季語:田打ち 春)
第二句集『山彦』からの句。明るく平明な表現が目立つようになっていく。「花桃」を季語に据えて、月の上る様を泉の湧くごとく「こんこんと」と捉える。隅々にまで力を込めて一枚の田を打つ農民の気概を「いつぱいに」と讃える。自らのスタイルを把握しつつある鴻司師がいる。
「なみなみと花屑泛ぶ吉野口」(季語:花屑 散った桜の花びら 春)
「月山のさんさんとあり蛇の衣」(季語:蛇の衣 へびのきぬ 蛇の抜殻のこと 夏)
「祭鉦ひときは洛中洛外図 」(季語:祭鉦 まつりがね 夏)
第三句集『頃日』で鴻司俳句は一気に花開く。「なみなみと」は、吉野口でこれから訪れる上流の花満開の吉野山を想像して、早くも胸を躍らせる師がいる。「月山の」は山中に無造作に脱ぎ捨てられた蛇の衣の纏う光に着目する感覚が鋭敏だ。「祭鉦」がひときは高まるとき、古の洛中洛外を夢想する師であった。
これらの句の核心には、それぞれ「なみなみと」、「さんさんと」、「ひときは」という副詞がある。師はこれら副詞の遣い方が絶妙だった。副詞は動詞や形容詞を修飾説明する役割の言葉だが、師は説明ではなく動詞や形容詞に膨らみを与える言葉として遣った。「なみなみと」は上流の桜が盛んに散っていることを暗示し、「さんさんと」は月の光を連想させる。「ひときは」に至っては、対象となる動詞や形容詞が消えてしまい、なんと「祭鉦」という名詞を副詞的に修飾している。言葉の仕組と役割を熟知した師ならではの妙技に、改めて感嘆するばかりだ。
「うららかや持薬に加ふ陀羅尼(だらに)助(すけ)」(季語:うららか 春)
「湯どうふのほぐれて嵯峨に雨少し」(季語:湯豆腐 冬)
「力まずにほどかれゐたる桑の瘤」(季語:桑ほどく 春)
「この頃や甘さが好きで走り藷」(季語:藷 いも 秋)
どれも成熟した人間性の発露がある。これらの句を収録した『頃日』で、師は一九九四年に俳人協会賞を受賞。祝賀句会が開かれ、その席で弟子たちが捧げた祝句全部にバツを付け、「お世辞の句はいらん」と気炎を上げた師の笑顔が忘れられない。
「ときどきはどぜうが上げる泥けむり」(季語:どぜう どじょう 夏)
「燈の入りてみるみる佞武多修羅となる」(季語:佞武多 ねぶた 秋)
「舟虫の一目散に子沢山」(季語:舟虫 夏)
「すかんぽやこだまうろうろしてゐたり」(季語:すかんぽ 春)
第四句集『平生』でも師の副詞マジックが輝く。「ときどきは」は植田で静かに進む稲の成長を見守り、「みるみる」は東北の祭のダイナミズムを表わし、「一目散」は「子沢山」とラッパーのように見事な韻を踏んでいる。「うろうろ」はこだまを擬人化するユーモアが秀逸だ。
「指さして春禽の名を忘れたる」(季語:春禽 しゅんきん 春)
「恐龍の尾を双六の振出しに」(季語:双六 すごろく 新年)
「減反のげんげ明りとなりたるよ」(季語:げんげ 春)
「指さして」は迎えた老境を逆手に取っておどけてみせる。こんな師との吟行は、本当に楽しい時間だった。「恐龍の」は老いてもなおの遊び心が横溢している。この茶目っ気も魅力的だった。一方で「減反の」は理不尽な農業政策へ警鐘を鳴らすかのような一句で、老いながらの気骨に背筋が伸びる。
「稲雀風の重たくなりにけり」(季語:稲雀 いなすずめ 秋)
落穂を腹いっぱいに食べた雀たちのいる田に吹く風が、どことなく重たく感じられるという。この感覚こそ、師が『頃日』以降に求めた境地だったのではないかと思う。
こうした句業のすべてを網羅した『吉田鴻司 全句集』は谷口摩耶氏や故・後藤兼志氏らの尽力により、二〇一一年に刊行された。師の没後二十年、結社『鴻』が二十年目に入る節目の年に読み返すのは、とても意味のあることだと思う。一人の俳人としての吉田鴻司の句の変遷は、『鴻』の連衆の今後におおいに参考になることだろう。北海道・倶知安に建立された師の句碑に刻まれた以下の句は、抒情性回復への願いを今も唱えている。
「羊蹄山の残照となる薯の花 鴻司」(季語:薯の花 夏)
俳句結社誌『鴻』2025年11月号
連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載