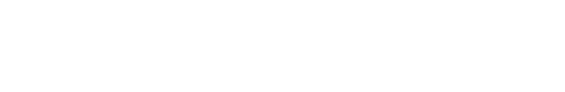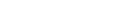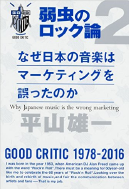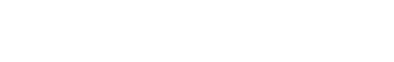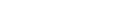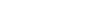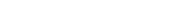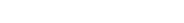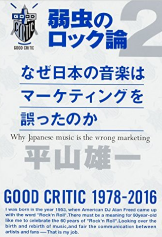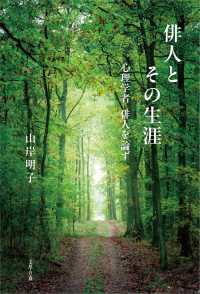
『俳人とその生涯』 山岸明子・著 文學の森・刊
このたび山岸明子氏が上梓した『俳人とその生涯』は、山本健吉評論賞『死刑囚・大道寺将司の生涯と俳句』の境地を一歩進めた快作だ。三年前の受賞の喜びに背中を押されて書いたというから、短期間での執筆に驚かされる。
サブタイトルに「心理学者 俳人を論ず」とあるように、対象となるのは境涯に何らかの問題を抱えた俳人たちである。それは当然のことで、何も問題のない俳人であれば創作の元となる心理的な葛藤や渡世の苦難は見られず、心理学者として触手が働かなかったのだろう。逆に言えば対象の俳人たちの実生活に踏み込むことで作品の鑑賞が変わってくるという危険がある。それを敢えて犯すにあたって氏は前書きで、自分の専門は発達心理学であり、何が彼らに俳句を詠ませ、俳句が彼らの精神生活にどんな影響を及ぼしたのかを自分なりに考察してみたいと書いている。
その意味で本書は純粋な俳句評論とは言えないかもしれず、限りなく作家論に近い。ただしその切り口は心理学に裏打ちされていて、情緒に流されずに俳人を追っていくうちに明子氏ならではの見解が浮かんでくる点が大変興味深い。
前衛俳人の折笠美秋は新聞記者として活躍していたときに難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症。目と唇以外は動かない状況になってからも妻のサポートを得て生涯俳句を詠み続けた。
「微笑が妻の慟哭 雪しんしん」(季語:雪 冬)
「ひかり野へ君なら蝶に乗れるだろう」(季語:蝶 春)
これらの句には献身的に看病する妻への感謝が込められている。美秋の置かれた状況からして、彼の句には自然と死にまつわるものが多い。ところが明子氏は美秋が発症以前から死の影をまとった句を作っていたと指摘する。
「死にごろとなり桃の木に桃登る」(季語:桃 秋)
「割れやすきものの音充ち銀河系」(季語:銀河 秋)
かつて美秋は自分の心の中にある私的な悲しみを絵空事=俳句で表現しようとしていた。しかし自らが死病にかかると、「死」を自分が赴く場所としてより具体的、現実的に詠むようになった。結果、彼の生来の明るさや優しさが「死」の句を通して発現したのではないかと明子氏は考察するのだった。
美秋の命を賭けた句作を検証するうちに、明子氏には思うことがあった。気軽に俳句を詠む者と真剣な自己表現を目指す者がいて、どちらが優れているとは言えないが、気軽に俳句を詠む者であっても、深い思いを持つ句に惹かれたり自分の中の深い思いに気づくことがあるのではないか。このくだりは実作者でもある明子氏の心境が生々しく感じられ、本書の注目ポイントになっている。
「雪はげし抱かれて息のつまりしこと 橋本多佳子」(季語:雪 冬)
多佳子は一般的に女性ならではの感性で情熱的な句を詠んだ俳人だと言われている。果たして本当にそうなのか。明子氏は定説とは別の角度から多佳子の作品を検討する。情熱的な句の対象であった夫を早くに亡くし、戦中戦後の大変な時期に四人の娘を女手ひとつで育てた。
「母と子に落葉の焔すぐ尽きぬ」(季語:落葉 冬)
「母と子のトランプ狐啼く夜なり」(季語:狐 冬)
困難な子育てをしながらも、これらの句には多佳子の心の充実が窺える。しかし「雪はげし」などの句は、未亡人でありながら恋に生きる女性と受け取る向きも多かった。確かに多佳子は「やるせない女心」を持ってはいたが、多佳子にしてみれば一生に一度の恋を思い返して詠っているのにもかかわらず、「やるせなさ」の根拠を誤解された作家だったと明子氏は指摘する。しかし多佳子にはそうした齟齬を受け入れる度量があり、すべてを飲み込んで「雪はげし書き遺すこと何ぞ多き」と人生の最後に詠んだのだろうという明子氏の見方が面白い。
「水洟や鼻の先だけ暮れ残る 芥川龍之介」(季語:水洟 みずはな 冬)
「兎も片耳垂るる大暑かな」(季語:大暑 夏)
本書の白眉は最後に置かれた芥川の項だ。短編小説の名手だった芥川は「我鬼」や「澄江堂」の号を持つ俳人でもあった。明子氏は芥川にとって小説・俳句とは何だったのか、彼を自殺に導いた苦しみに小説や俳句がどう関与したのかを考察する。芥川にとって小説は内面にある書きたいものを表現する重要な手段であり、俳句は自分が見たり感じたりすることを即興的に詠む「余技」だった。それだけに俳句を通じて気楽に付き合える友人も多く、芥川にとって楽しいものだったという。
「水洟」は辞世の句で、芥川の生涯を覆い尽くす凄絶な苦しみを、闇からぬっと現れた鼻が象徴しているという解釈がなされている。しかし明子氏によれば芥川の作った句は明るく気さくなものが多く、「兎」はその代表的な例だという。ただ龍之介は生母の発狂といった事実への不安など、小説で自分の内面を出すことを怖れていた。対して俳句は自分を曝さずに世界と関わり、他者に理解される。この「詩歌療法」が芥川の精神病理の緩和に有効だったのではないかと明子氏は説く。このあたりがこれまでの俳人論とは異なり、心理学者としての独自の見解が顕われていて感服したのだった。
本書は膨大な資料を踏まえた労作と言える。それだけに座学的傾向が強すぎる一冊でもある。明子氏は実作も行なっているのだから周囲の俳人ともっと議論を交わし、実作者としての側面も活かせばより論が深まったと思う。それはともかく、上梓、おめでとうございます。
「葡萄食ふ一語一語の如くにて 草田男」(季語:葡萄 ぶどう 秋)
俳句結社誌『鴻』2025年7月号
連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載