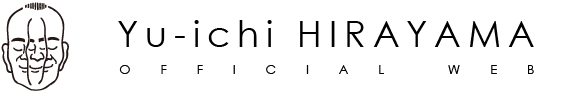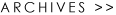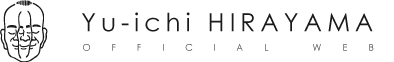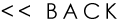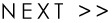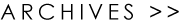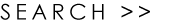[caption id="attachment_261" align="aligncenter" width="480"] 201612071601[/caption]
201612071601[/caption]
RED WARRIORSは解散を経験してから成熟した。『FIRE DROPS』は、それを証明する傑作だ。(RED WARRIORS『FIRE DROPS』ライナーノーツより)
音楽評論家 平山雄一
1986年、彗星のように日本のロックシーンに現われ、『LESSON 1』、『CASINO DRIVE』、『KING`S』、『Swingin`Daze』の4枚のオリジナル・アルバムを残して、1989年の武道館2daysライブを最後に解散したRED WARRIORS。デビュー前年の1985年にハウンドドッグが「ff(フォルティシモ)」で、レベッカが「フレンズ」でブレイクを果たして始まったバンドブームに、RED WARRIORSは予想外の角度から名乗りを上げたのだった。
オリジナル・メンバーは、ダイアモンド☆ユカイ(vo)、SHAKE(g)、小川清史(b)、小沼達也(dr)の4人。当時はポップなロックやビートパンクのバンドがほとんどだった中で、RED WARRIORSのオーセンティックなロックは異彩を放っていた。わかりやすく言えば、それまでのロック=不良という公式を離れて、普通の若者も楽しめるロックとして80年代のバンドブームはスタートしたのだが、RED WARRIORSはロック=不良という公式どおりの音楽とパフォーマンスを展開。やがてこの“ユニークな本格派バンド”は人気を得て、他のバンドとは一線を画す存在感を発揮する。そして、あまりにもいさぎのよい散り方に、RED WARRIORSは伝説となった。
その後、1996年のライブのための再結成の流れを受けて、1997年に発表されたのが本作『FIRE DROPS』である。
今回、再発売された『FIRE DROPS』のライナーノーツのために、ユカイ、SHAKE、小川の協力を得て、それぞれのインタビューを敢行した。『FIRE DROPS』から20年が経った今、メンバーにRED WARRIORSの歴史を振り返ってもらうと、当時は謎に包まれていた彼らの内面が伝わってくる発言が相次いだ。
そうした貴重な言葉で構成されたライナーノーツの一部を抜粋して、音楽ファンに読んでいただきたいと思う。その上で『FIRE DROPS』に興味を持つ方がいたら、ぜひ聴いてもらいたいと思う。このアルバムは間違いなく、発表から20年以上を経てもなお新鮮に響くロックアルバムの傑作だからだ。
〈ダイアモンド☆ユカイ〉
今思うとね、結成前はメンバーそれぞれみんな、別々の立ち位置でいたんだよ。もともとレベッカっていうバンドでデビューしてたSHAKEと小沼くんがいて、ローディーをやってた清史がいて。俺だけが“業界”を知らなかった。
俺はホントにただもうロックが歌いたいっていうだけの、何にもかもまっさらの状態だった。一緒にやることになって、ともかくバンドで歌えるっていう喜びしかなかったような気がする。
実はSHAKEとはその前にも、一回「バンド組もうか」みたいな話があったんだけど、俺の方が断っちゃった(苦笑)。ただ埼玉のホントに小さいバンドの集まりの中でね、俺は「SHAKEって、いい曲を書く奴だなあ」って思っててさ、SHAKEは俺のことを「ロックな歌をうたう奴だ」って思ってて、俺とやりたかったんじゃないのかな。
〈SHAKE〉
俺はレベッカで1984年にデビューして、間もなく辞めた。当時、デビューするっていうのは、国家試験に合格するっていうぐらいのことで、事務所やレコード会社の言うことを聞かなくちゃ、デビューできなかった。で、自分のできるロックの中でも最もポップの瀬戸際までやったんだけど、それでも揉めてレコーディングも大変だった。おまけにファーストアルバムなんて3000枚くらいしか売れなかった。報われなかったね。
それでも「レコードを出す」っていう目的は果たせたから、だったら辞めて、売れなくてもいいからいちばん好きな“ロックの真ん中”をやろうと思った。
21才の時にアメリカに行って、ロックというものはこういうものだったのかというのを肌で知った。その開放感をやりたかったし、日本の人たちにも知ってほしくて、まあ、当時の日本では売れるわけないなと思いながら、RED WARRIORSの音楽を途中からR&R一直線に切り替えた。
RED WARRIORSは、ブルースロックを基本にしている。他のバンドが“歌謡ロック”とか“青春パンク”をやってる時代にだよ。絶対に日本の風土からは生まれない、コンセプチュアルなバンドだった。それが、デビューしてみたらヒットチャートに入ったんだから、面白いよね。笑いが止まんなかったよ(笑)。
80年代のバンドブームは、別な言い方をすれば、“日本のリスナーに合ったロック”が基本になっていた。元々、SHAKEが在籍したレベッカは、SHAKEが脱退した後、日本に合わせたロックの代表例として成功したバンドだった。そのSHAKEが新しく組んだRED WARRIORSは、レベッカとは真逆の指向を持っていたのに、結局は人気バンドにのし上がっていったのだから歴史は面白い。バンドブームの主流からは完全に外れていたRED WARRIORSの快進撃を、メンバー自身はどう感じていたのだろうか。
現在、釧路湿原で宿泊施設を経営しており、カヌーのインストラクターもつとめている小川清史は、当時をこう振り返る。
〈小川清史〉
RED WARRIORSは、激動のバンドブームの最前線にいた。武道館ライブもやったし、今でも日本中にRED WARRIORSを知ってる人がいる。釧路でも俺を知ってる人がいるって、最初はびっくりしたよ。
解散したときは25才だった。今、思えば、自分にとって本当に大きな経験だった。夢のような時間だったよね。
〈ダイアモンド☆ユカイ〉
今、RED WARRIORSを振り返ると、楽しいことばっかりじゃなかったけど(苦笑)、青春だね、うん。正直、当時は苦しかった。楽しむっていうよりも、がむしゃらにやってくことで、無理やり前に進んでたっていうか。
俺、デビューしたのが23才で、27才で解散して。ロックだったら“ゴールデンエイジ”だったなあと思って(笑)。ジミ・ヘン(ドリックス)とかジャニス(・ジョプリン)みたいに27才で死んでたら、たぶん伝説になってたね(笑)。ゴールデンエイジのときにRED WARRIORSとして自分がバンドをできたことは、すごく幸せなことかなあって今は思うね。
あの頃は、BOΦWYやブルーハーツがいて、BOΦWYはちゃんとポップな音楽をやって、今に至るまで続くような真面目なファンが多かった気がする。で、ブルーハーツはどっちかっていうと、歌詞が文学的だった。小説とか本とか読むような子たちがファンだった。
RED WARRIORSは、たぶんいちばん感覚的なバンドだったんじゃないの。カッコイイかカッコ悪いか。基準はそこにしかなくて。その中で、自分たちが憧れたロックの世界っていうのを日本語で表現することを一生懸命やってきた。少なくとも俺とSHAKEはそういうふうに思ってたと思うよ。やってくうちに曲作ったりとかソングライトの部分では、どんどん成長していった。
バンドが一気に階段を駆けあがってくうちに、メンバーそれぞれの役割みたいなのはできてたのかもしれないね。音楽的なことはSHAKEがやって、ライブはボーカルの俺が中心になってやってた。俺の中には最初っからエンターテイメントっていうものがあって、ライブを観に来てる人を「喜ばせたい」とか、「カッコ良く見せたい」って思ってた。カッコイイ/カッコ悪いっていうのはロックの最初の基本。俺もそう思ってたけど、バンドの中では誰よりもSHAKEがいちばんこだわってたと思う。で、後半になってくると、メンバーみんな、自己主張が激しかったから、ぶつかるようになっていった。
RED WARRIORSって、あっという間に終わっちゃったんだよ。今思うと、早回りで駆け上がって、上がった途端に潰しちゃったようなもんだからね。世の中の状況もわからずに、自分たちしか見えなくなってた。解散も、止めようと思えば止められたかもしれない。だけど、なんか俺も解散のほうがいいなと思っちゃった(苦笑)。
解散後、SHAKEはアメリカに渡った。ユカイはソロ・アーティストとして1990年に傑作『I`M THE BEST-世界の女は俺のもの-』を発表。小川は自分の道の模索に入った。
解散から7年が経って、96年に3人が再び集まり、武道館ライブを敢行。翌97年3月に本作『FIRE DROPS』がリリースされたのだった。
〈SHAKE〉
アメリカにいた5年半で、アルバムを3枚作った。それでも自分の音楽を確立したって思えなくて、試行錯誤してたね。結局、ロック云々ではない自分自身で音楽をやっていかないとと思って。「ロックだ、ロックだ」って言って周りを蹴散らしてきた人生を、初めて後悔した。そうしたら「そうだ、俺はサイモン&ガーファンクルとかも好きだったんだ」って“柔らかい自分”を思い出した。ロックっていうヨロイを脱いで、クラシックを聴いてみたり、60年代のロックのことを調べたり、アメリカ大陸を横断してみたり。破壊して残るものが自分なんだって。自分の中で革命が起こったんだよね。
そのうちにロックバンドとしての理想像のような物があらたに見えてきて、地球にも人間にも“黒いエネルギー”があるって気が付いた。怒りとかケモノ的な感情を、自分は有機的なものとして出そうと思ったけど、そういう音楽を歌えるとしたら、ユカイくんしかないと思った。
〈ダイアモンド☆ユカイ〉
アメリカからSHAKEが帰ってきて、いろんな紆余曲折があって、もう一回「やろう」っていう話になった。で、アルバムを作り始めたら、初期のRED WARRIORSよりもサウンドがもっとプロフェッショナルになってるから、解散前より断然ロックっていうか、「本当のロックをやろう! やっとそれができるんだ!」みたいな気持ちになったよね。
この『FIRE DROPS』のSHAKEの作った歌で「俺以外には歌えねえだろ」っていちばん感じるのは「ONE WAY DRIVER」かな。こういうのは、自分では作れないんだ、表現はできるけど。だからある意味、「ONE WAY DRIVER」は、RED WARRIORS以外の何ものでもないかもね、他のバンドにはできない。
〈小川清史〉
解散前は、できるだけSHAKEのイメージに近づけようってプレイしてたけど、『FIRE DROPS』では一人のベーシストとして参加している自分がいた。みんなでセッションしてできたリフを1曲にしたり、楽しいレコーディングだったね。このアルバムを作ったことで、自分が解放された。昔とは違う自分がいた。
きっと一回、解散しないと『FIRE DROPS』はできなかったと思う。俺にとって、RED WARRIORSが自分をさらけ出す場所になった。
無邪気に喜ぶ3人の言葉が、『FIRE DROPS』というアルバムの真価を表わしている。そんなアルバムの再発売は、日本の音楽シーンにとって、とても幸せなことだ。
3人のメンバーの心の内を、今、知ることができるのは、ファンとして幸運なことだと思う。真剣にバンドに向き合う3人は、RED WARRIORSを真剣に愛していた。そうした気持ちをほとんど言葉にしてこなかったメンバーの思いを、このインタビュー・ダイジェストで少しでも感じていただけたら幸いだ。
RED WARRIORS は、J-ROCK史上、まれにみる“ロックバンド”だった。これほどのテンションでぶつかり合うバンドが、かつていただろうか。同時に、これほどメンバーがお互いをリスペクトしているバンドも珍しい。ある意味、とてもクレバーなミュージシャンたちを、コントロール不能になるほど熱くさせる。これこそがロックバンドの魔法と言うべきだろう。
『FIRE DROPS』の再発売を機に、バンドブームとはなんだったのか、あるいは今のJ-ROCKの在り方や未来について思いをめぐらせてみることも楽しいだろう。ダイアモンド☆ユカイやSHAKEや清史の魂が一瞬間交わった軌跡は、今も美しい。
これまで多くのバンドが再結成を果たしてきた。だが、解散前を超えるアルバムを作ることのできたバンドはほとんどいない。そして『FIRE DROPS』は“超えている”。このインタビュー・ダイジェストの最後は、ダイアモンド☆ユカイの言葉を引用して締めくくろうと思う。
「でもさ、RED WARRIORSに出会えてさ、俺は良かったと思ってる」。