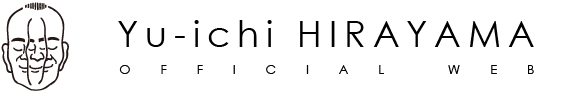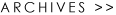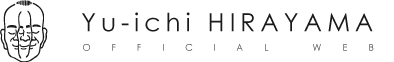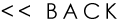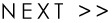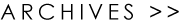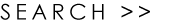2016年、35周年を迎えた布袋寅泰は日本を代表するアーティストであり、世界的な評価を獲得している数少ないミュージシャンだ。
布袋の名を世に知らしめたのは、BOØWYだった。僕は幸運にもデビュー前のBOØWYを間近で見たことがある。1981年、僕の友人のミュージシャンが「面白いバンドがいる」と、渋谷にあった小さなスタジオに連れていってくれた。BOØWYはそこでレコーディングのリハーサルをしていた。長身の布袋は、狭いスタジオの中で異様な存在感を放っていた。そして存在感以上に、鋭いギタープレイが僕に強烈な印象を残した。リズムを刻むコード・カッティングの技術が、飛び抜けてシャープだったのである。1980年代初頭の日本のバンドシーンでは、“ギター・ソロ”を第一に考えるギタリストが多かった。だが布袋はグルーヴ重視という、斬新なアプローチを持っていた。
BOØWY時代の布袋の特徴として、もう一つ挙げられるのは、“ギター・リフ”だろう。「BAD FEELING」のイントロに代表されるリフは、一度聴いたら忘れられない魔力を持つ。ギター・ソロを必要以上に重要視せず、グルーヴを最優先した布袋だからこそのオリジナリティがここにある。
布袋はBOØWYを解散した88年に『GUTARHYTHM』でソロ・デビューした。このファーストアルバムには、その後の彼の展開を予言する要素が数多く入っている。徹底的に洋楽を意識した音楽作りは、世界進出を予感させる。ギターをメインにしたインストルメンタルという部分では、その後の映画音楽への進出の伏線になっている。そしてボーカリストへの転進も意識されていた。
『GUTARHYTHM』で自らの未来を示した88年に、布袋は吉川晃司とCOMPLEXを結成。BOØWYでの経験を完全に客観視した布袋は、“ボーカルとギター”というツートップ・スタイルのユニットの頂点を極める。
ここから布袋は本格的なソロ活動に入り、“日本のロック・ボーカリスト”という、まったく新しいジャンルに挑戦することになる。洋楽指向だった『GUTARHYTHM』とは異なり、『GUTARHYTHM Ⅱ』で日本のリスナーを強く意識した曲作りにトライする。別の見方をすれば、“新進ロック・ボーカリスト布袋”のために曲を作り始めたとも言えるだろう。それは間もなく開花して、「LONELY★WILD」(92年)、「さらば青春の光」(93年)、「サレンダー」(94年)など次々とヒットが生まれ、ソロ活動は軌道に乗っていく。
ここで注目したいのは、“ソングライター布袋”から渡された楽曲を、“ボーカリスト布袋”が見事に歌いこなしたことだろう。手探りで始めたボーカルだからこそ、スムーズでない部分も含めて、ロッカーとしての生き様をリアルに伝えることができた。これもまた布袋のオリジナリティだった。その説得力のあるボーカルは感動を呼び、現在でも布袋が多くの男性ファンを持っていることの一因となっている。
“ボーカリスト布袋”とともに、もう一つ90年代で見逃せないのは、インストルメンタルの側面だ。特に重要だったのは、94年に奈良・東大寺で行なわれたイベント“AONIYOSHI”でのマイケル・ケイメンとの出会いだろう。マイケルは『未来世紀ブラジル』や『ロビン・フッド』(第34回グラミー賞)などの映画音楽を多数手掛けていた。意気投合した布袋はマイケルのオファーを受けて、アトランタ五輪閉会式(96年)の演奏に加わる。さらにはギターとオーケストラの融合作品『GUITAR CONCERTO』にも参加した。
この経験は、布袋にワールドワイドな展望を与えたエポックメイキングなものだった。マイケルは残念ながら2003年に亡くなったが、その年にクエンティン・タランティーノ監督の映画『キル・ビル』のテーマに「Battle Without Honor or Humanity」が起用されたのは、偶然ではなかったのかもしれない。その際の布袋の対応は、これまでの日本人ミュージシャンの誰とも違う堂々としたものだった。このアティチュードは、布袋がマイケルから受け継いだものの一つに思えてならない。
布袋のインストや映画音楽は、初期の頃からクオリティが高かったが、ボーカリストとしての経験やマイケルとの交流が、彼のオリジナリティをさらに磨いたに違いない。
21世紀に入ると、布袋の活動は自由度を増していく。Charと元ストレイ・キャッツのブライアン・セッツァーを迎えて、思い切りプレイした夢のようなイベント『HOTEI presents“SUPER SOUL SESSIONS”BRIAN SETZER vs HOTEI vs CHAR』(07年)を開催。先輩も後輩も国籍も関係ないセッションは、布袋の柔軟な音楽性を自然に引き出していた。
2012年、2月1日に布袋は50歳の誕生日を迎えた。記念ライブのさいたまスーパーアリーナでは、オープニングからBOØWY 、COMPLEX、GUTARHYTHMの曲がランダムに歌われる。それこそ布袋のオリジナリティのオンパレードだった。
このライブで一つの区切りを付けたかのように、この年の夏、布袋はロンドンに居を移す。理由は「ずっと世界で活躍することを夢見てきた」。実際、彼は永年、ロンドンを第二の故郷のように往復してきた。その地で50歳にしてゼロから出発としようと言うのだ。世界進出のハードルは非常に高い。だがそこにあえて踏み込むのが、いかにも布袋らしい。
もしかすると、この“世界に向かう意志”こそが、布袋の最大のオリジナリティなのかもしれない。音楽のジャンルやプレイスタイルを軽々と超えて、ワールドワイドなロック・ギタリストとして存在したいという意志。それは少年の頃からの布袋の夢だった。
「夢を果たす」、そこに布袋のオリジナリティの源泉がある。
[エンタメステーションのアーティクル・ダイジェスト]
http://entertainmentstation.jp/