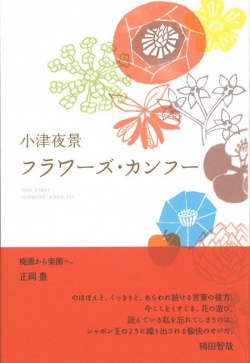
句集『フラワーズ・カンフー』 小津夜景・著 ふらんす堂・刊
小津夜景は、南仏在住の女流作家。昨年(2016年)、上梓して話題になった第一句集『フラワーズ・カンフー』が、今年(2017年)の第8回田中裕明賞を受賞した。おめでとうございます。
第7回受賞作はこの連載でも紹介した北大路翼の『天使の涎』、第6回は鴇田智哉の『凧と円柱』、第3回は関悦史の『六十億本の回転する曲がつた棒』など、この賞は個性的な作家を世に出すことに多大な貢献をしている。また、ようやく若手の育成に取り組み始めた俳人協会に、決定的に不足しているものを補う役割を見事に果たしている。
俳人協会に足りないものとは、作家のプラスの部分を評価すること。「技術が足りない」や「将来が危うい」などのマイナス面ばかりに言及して、眼前の作品そのものや作家の持つ可能性を否定的に見る傾向がある。そして『フラワーズ・カンフー』は、そうした観点から見れば、問題山積みの面白い句集なのである。
問題の第一は、小津には言葉の遊びを最優先に考えている節があることだ。
「うららかを捧げもつ手の手ぶらかな」(季語:うららか 春)
「ぷろぺらのぷるんぷるんと花の宵」(季語:花 意味:桜 春)
これらの句は、言い回しの面白さや、言葉の持つ音の遊びから成り立っている。
「しはぶきにたなびく旅の雲のこと」(季語:しはぶき 意味:咳 冬)
「またとなき日がまたの名を名告りけり」
「しはぶき」の句は、“たなびく”の“た”と“び”から“旅”へと繋がって、心地よいリズムを生んでいる。「またとなき」の句はダジャレ寸前ながら、前述の「うららか」の句と同様の軽快さが持ち味だ。残念ながら季語が入っていないが、作者が“俳句のリズム”を楽しんでいるのは明白である。これらの句には「言葉遊びで作るな」だの「作者の人間が感じられない」だのという、いろんな苦言が聞こえてきそうだ。
しかしその延長上に、いくつかのオリジナリティの高い句が生まれている。
「あさがほのかたちで空を支へあふ」(季語:あさがほ 秋)
「鳴る胸に触れたら雲雀なのでした」(季語:雲雀 ひばり 春)
「アルバムに日付のなくてあたたかし」(季語:あたたか 春)
「スプーンを舐めて高きに上るかな」(季語:高きに上る 秋)
小津ならではの、瑞々しい句群だ。「あさがほ」は「支へあふ」とする広がりのある発想がいい。「雲雀」は口語の生む親近感を、効果的に使っている。「アルバム」はおおらかで表現の間口が広いし、「スプーン」は動きのある颯爽とした叙述が気持ち良い。
こうした開放的な句は、小津が俳句を“自分個人のもの”にしているところから生まれている。他からとやかく言われる筋合いはないと、言わんばかりの自由さがある。すべてが成功作とは思わないが、突出した個性は自由な句作りから発生していることは間違いない。
一方で僕は、『フラワーズ・カンフー』収録句の7割が理解できなかった。句の意味が分からなかったり、形式が不可解だったりした。たとえば〈八田木枯句の主題による短歌〉で成る「こころに鳥が」の章や、文語表記によるエッセイに俳句を挟み込んだ「天蓋に埋もれる家」の章は、良さが全然わからなかった。
しかしそれらは小津にとって、この句集を構成するにあたってどうしても必要な章であったらしい。北大路が一見乱暴そうに見えて、実はエンターテイメントを考えた句集作りをしているのに対して、小津はエンターテイメントをほとんど意識していない。それは小津の表現者としての一つの特性にもなっている。
また、あとがきに気になる文章があった。
「出アラバヤ記」が攝津幸彦賞の準賞となったのを機に俳句を始めてから途方もなく長い二年半が経過した。この間しばしば思い出したのは「前衛であるとは死んだものが何であるかを知っているということ、そして後衛であるとは死んだものをまだ愛しているということだ」といったロラン・バルトの言葉である。
小津はその自由な作風から“前衛”と思われがちだが、実は“後衛”も試みている。句集の最終ページには次の句があった。
「ともづなに蛍をともす夜さりかな」(季語:蛍 夏)
「くらげみな廃墟とならむ夢のあと」(季語:くらげ 夏)
恐ろしく古めかしい句である。そして、これらもまた小津夜景の句なのである。
「朧夜がなにもない巣を抱いてゐる」(季語:朧 春)
「ほうと吐き一糸まとはぬ月自身」(季語:月 秋)
「夜の桃とみれば乙女のされかうべ」(季語:桃 秋)
これらは小津が発見した新しい俳句ファンタジーと言えるものだろう。卵も親鳥もいない巣を抱く「朧夜」は、無事に巣立ちを終えた一組の鳥の家族の歴史を思わせる。
「月」を繭として幻視し、糸を吐きながら「自身」にそれを纏わないという描写は、白く輝く月の裸身を想起させる。「夜の桃」は、坂口安吾の描く奇譚のように、残酷で美しい。
そうして小津は、自分の行なっている“言葉の遊び”を次の句に集約する。
「言の葉に効く毒抜きはいらんかね」
小津は、俳句の外側から俳句を作っている。なので、『フラワーズ・カンフー』を読んでいると、「こんな俳句があるんだ」とか、「こんな俳句があってもいい」という思いにしばしば駆られる。すなわち、それが俳句の可能性だ。それを汲み取る田中裕明賞を目指す若手俳人が、今後一段と増えることだろう。
「いまだ目を開かざるもの文字と虹 小津夜景」(季語:虹 夏)
俳句結社誌「鴻」2017年7月号コラム【ON THE STREET】より





















